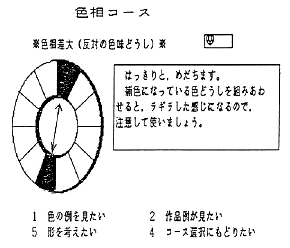2. コース名及び特徴
●『四方連続模様のシミュレーションコース』(0.5時間)
このコースでは四方連続模様を理屈で修得するのではなく、シュミレーションを通して体験的に学習することが狙いである。
ユニットを並べ変えてつくる四方連続模様は、頭の中だけで構成するのは難しい。生徒は、自分の試してみたいユニットを4つの中から選び画面の中の縦5列横5列のますの中に組み入れていくことができます。一度、組み込んだものは、繰り返し模様の並べ変えができ、四方連続模様の並べ方を体験的に修得できます。また、修得の早い生徒や、ユニットを変えたい生徒がもう一度違うユニットを使って学習したい場合教師がキーワードを入力することで再学習ができる。
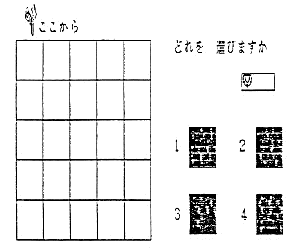
●『形の考え方コース』(1.0時間)
ユニットを並べたとき、すっきり見えるようにするために注意することを考えさせるコースである。
並べたときにすっきり見えるユニットと、模様がはずれてしまうユニットを組み込んだシュミレーションを比較し、その違いを話し合うことで、形の考え方が理解できる。形を考えるのは色を考えることよりも難しくコンピュータのシュミレーションを通しての体験学習では対応が困難である。そのため、一斉授業の中にコースを組み入れ、コンピュータを使っての学習→話合い学習→発表→コンピュータを使っての学→……と確実に学習していくことが大切になる。それによって、生徒は抵抗なく形の考え方が理解できるのである。
●『形を考えるコース』(1.0時間)
『形の考え方コース』で学習したことを確認するコース。
すっきり見えるためのポイントや、ユニットの例が見られる。ユニットの例は、「二等分点をつかっているもの」「角と角を線で結んだもの」などのがあり、それぞれの例はループして見ることができるため、必要な情報に戻して繰り返し見ることができる。
このコースではユニットの構想を練るための時間を多くとりたいのでコースそのものはできるだけ簡潔な方がよい。
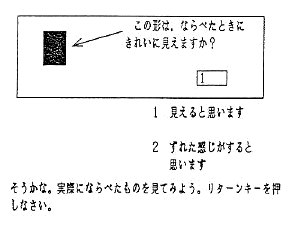
●『色を考えるコース』(0.5時間〜1.0時間)
配色のための一助になるコースである。
生徒は、ユニットの配色のためにテーマを持つ。色の感情の暖かい色、寒い色、明るい色、暗い色、軽い色、重い色、高彩度色、低彩度色、高明度色、低明度色……などがそれであり、そういった配色をテーマとすることで、色の基本的な知識の定着を図ることが目的である。
それぞれの色のコースの中は、色についてのテキストと、色の例、作品の例になっており、それぞれループさせることができる。また、色のコースそれぞれの間もループさせることができる。生徒は、必要だと思う場合自分のテーマにあった色のコースを選択し情報を収集することができる。