2. 実践と反省
(1)授業を終えて
1 児童の反応(学習制御データの分析)
- 目標設定は、分数×整数の計算ができることとし、F1120まで到達するよう作成した。その結果、24名中全員がF1120を通過することができた。目標設定としては、良かった。
- 立式においては、かけ算(1/7×3)で答えた児童が17名、たし算(1/7+1/7+1/7)が5名、1/7+3が2名で、かけ算以外あるいは誤答の児童あわせて、7名であった。
つまずきの2名については、No.21の児童は、はじめ1/7×3を1/7+3と答えていたが治療コースを通過することにより、次の問題においては2/7+2/7+2/7と立式することができた。もうひとりNo.24の児童は、治療コースでは1/7×2と表示したにもかかわらずメインコースにもどり、2回ともたし算で立式をしていた。
- 1/7×3の計算を3/21と答えた児童は、1名でF0040で治療されていたが、その時はじめの問題では(4/7 リットル.7リットル.21)と4回ともまちがっていたが、次の問題では、1回で正答になり治療されたことになる。治療コースで要した時間は、3分43秒を要した。
1/7×3=1/21を答える児童は、いなかった。
その他の誤答については、4名の児童がいた。3/21と答えた児童を含め5名の誤答がいることになる。その5名の児童はF2710のコースへ進み、シュミレーションにより説明され、メインコース(F1070)の文章題の2/7×3の立式に進んだ。2人のつまずき(たし算でやった。)はいたが、計算では全員できた。しかし、1/7×3から2/7×3の分子だけの交換の立式であったため全員が計算できたのではないかと考えられる。そこで、分数の形をかえ、1/3×2の計算で判定してみたら、この計算も全員が正答であった。このことから、分数×整数の計算の仕方は、24名の児童については、理解されたとみる。
- 目標と設定されたF1120を進み、練習問題コースになるが、計算をし仮分数になった場合帯分数に直す治療コース(F4000)があるが、そのコースを通過した児童は、いない。また、約分コースも同様で治療することなく、メインコースを進んでいることがわかる。でもこの2コースは理解の速い児童しか通過していないので、理解の遅い児童は、まだここまでは、進んでいないことになる。
- 理解の速い児童について、約分の仕方は、答えを出して約分した児童が多く14名もいた。その14名の児童は、F7000へ進み計算の途中で約分する練習をしたことになる。
- 理解の速い児童がどこまで進んだか調べたら、分数のかけ算コースを終了した児童が8名もいた。この分数のかけ算コース(1時間のソフト)は一斉授業では、2〜3時間分の内容である。このことから一斉授業では足ぶみ状態であった児童にとってもすくわれたことになる。
(2)コンピュータを導入して
- 一斉授業においては、教師と学習をより理解している児童によって、児童が進められがちであるが、コンピュータでの学習では、コンピュータ1台につき、児童1人の1対1での学習であるので、主体が個にある。自分で解けない問題にぶつかると、わかるまで次に進めないことになる。そのため、じっくり考え試行錯誤しなければ立ち往生するので(一斉授業では、誰かが考えるのでは…といったところもあるが)コンピュータにくいいるようになる。もし、1人で問題解決できない場合でも、それぞれのつまずきにより、いくつかのコースに進み治療されるので個人個人の学習ができることになる。
このようなことから、机間巡視をしても、見落としがちである、つまずきをコンピュータでの授業では、個々のつまずきを見つけ事後指導に役立つ。
また、一人ひとりのノートを調べデータ収集するには、数時間かかるが、コンピュータでのデータ収集は、学習制御データにより、必要な学習記録を出すことができるので、そんなに手間どらず確実な情報を得ることができる。
(3)ソフト内容について
説明を減らして、児童の反応をみながら学習を進めた。
説明のフレームが3フレーム以上続かないように工夫した。
類似問題を2〜3回くり返したのは、より理解しやすかった。
真分数×整数=真分数(約分のいらない分数)の問題から、答えが分数から帯分数へ直したり、分数のないものから分数のある計算へと出題したのは、児童の理解の上からも、教師が実態把握する上からも良かった。
修正したい箇所
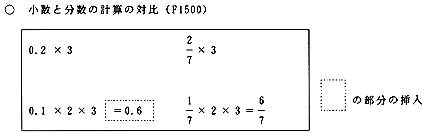
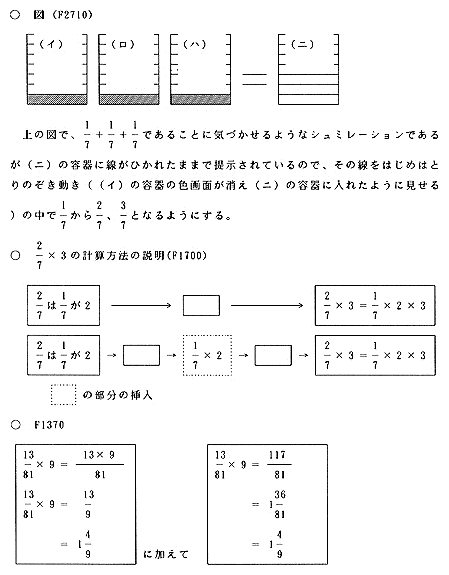
(4)感想
<教師>
- コンピュータでの学習は、どの児童にとってもワクワクするようである。期待とキーのおしまちがいはしないか…などの不安の中で授業がスタートした。あまりの緊張で手に汗をにぎりキーをおすのがおくれがちだった女の子。その反対にポンポンとキーをおしすぎて画面に出てきたものを理解せずに進み”しまったー”と思いながらやっている男の子。自分が解いた問題が正答になりメッセージを見て”やったね”とニコリとしながら次の問題へ進む子。全てのコースを終わり自信をもった子…など
いろいろな表情の中で進められた。
いろいろな性格や、いろいろな理解度のある児童一人ひとりが、本当に真剣に取り組み楽しく学習できた。
<児童>
- コンピュータの授業をして良かったところは、ちゃんと説明して(グラフとかの説明)わかりやすかった。でも、読むのに時間がかかった。
- ふだんの授業より、一人でできるし、自分の進める所まで絵やかんたんな文でわかりやすくできているのでまたやりたい。
- わからない所はわかるまでやるのがいい。
- しゃべるコンピュータがいい(希望)
- 図や言葉で表わすのはとてもやりやすかった。でも、<エンターキー>をおすとすぐその場面がきえるのは気にいらない。
- コンピュータにはキーがたくさんあってまぎらわしいけど、説明とかわかりやすいので何回もやりたい。
(5)今後の課題
- ノートをとらせる箇所をどうするか。
- 問題提示の仕方の工夫
<たとえば>
- 発問の仕方(言葉)
- 画面表示(文字や図・色・大きさ)
- 個にあったコースウェアの作成にあたっては、児童の実態分析をどのようにするか研究を深めたい。