3. コースウェアの概要
1.コースウェアの全体構造図
2.コースウェアの組み立て
このコースは、1学年初期の学習能力に合うように、文字を大きくし、また言葉での説明やメッセージを少なくした。またその反面イラストによる表示を多く活用した。学習者が理解出来にくい所では、常に教師の指導をうけることができる。
ドリルを終了した時点で、学習態度、学習時間等によって学習を継続するか終了するかを、教師が選択できる。
コースは、大きく3つのステップに分れる。
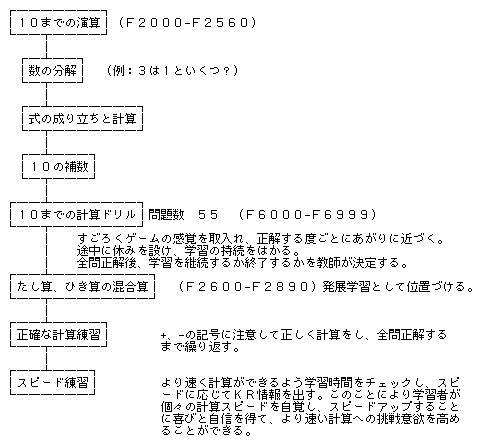
3.学習者に求められる活動・思考
◇10までの演算(F2000-F2130)
はじめに、5までの数について、イラスト表示での具体物を視覚的にとらえ、数字との対応、強いては数を理解する。
数の分解のしくみをイラストの動きによりとらえ、それが数式に置き換えられることを知る。
数式だけを使って、計算を試みる。誤答の場合は、イラストを見て数をかぞえ再び
解答することができる。
1ブロック3問の問に答え、2問正解であれば次へ、それ以下であれば、はじめの問題にもどって計算する。これを2回繰り返すと、教師の指導をうける。
同じパターンで10までの数の計算、10の補数を学習する。(F2140-F2560)
◇10までの計算ドリル(F6000-F6999)
問題数55題の計算ドリルに入る。1問ずつ掲示される問題を解き、イラスト表示によって正解であったかどうかを判断する。
全問正解であれば、学習を続けてもよいかを教師に判断してもらう。誤答があれば、その問題をできるまで繰り返す。
途中休憩や、謎ときをして次の学習への意欲を高める。
◇たし算、ひき算の混合算(F2600-F2890)
混合算の計算練習に入る。+、-の記号に注意して正しく計算をする。全問正解を得られなかった時は、誤答の問題のみ再試行する。
つぎは、各自がどの位の速さで計算ができるかを知り、より速くより正しく計算できるよう努力する。(F2710-F2800)
4.教師の役割
ドリルに入る前の段階で、2回試行の末、全問正解にいたらない学習者には、教師の指導を求めるように指示が用意されている。教師はその学習者に対してすみやかに、適切な指導をする。
ドリルでは、正答表示のイラストの変化により学習者の進行状況を知ることができる。それを観察しながら個々の学習者にあった、励ましや問いかけが必要である。
ドリルが終了した時点で、学習を続けるか終了するかの決定が教師に求められる。授業の経過時間や学習者の学習意欲等の状態から判断して、適切な決定を下す。その際、学習者が納得できる言葉かけが望まれる。